AIの暴走を防ぐ方法
生成AIは便利なツールですが、使い方によっては思わぬ問題を引き起こすこともあります。
1. 今日のテーマ
責任ある「AI使い」になるために必要な知識を身につけましょう。
2. AI利用の倫理ガードライン
差別的発言を防ぐ
生成AIは大量のインターネット上のテキストを学習していますが、そのデータには偏見や差別的な内容も含まれています。そのため:
- AIに特定の人種、性別、宗教などについて否定的に語らせるようなプロンプトは避ける
- AIの回答に偏見や差別的な表現があった場合は、それを指摘し修正を求める
- 自分の持つ偏見にも注意し、AIに求める内容を見直す習慣をつける
例)「〇〇人の特徴を教えて」→「〇〇の文化や歴史の特徴について教えて」
個人情報保護の徹底
AIとの会話はデータとして保存されることがあります:
- 自分や他人の実名、住所、電話番号などの個人情報をAIに入力しない
- 学校名や具体的な所属などもできるだけ避ける
- 特に友達や家族の情報を無断でAIに入力しない
例)「私の友達の田中さんは〜」→「ある友人は〜」
著作権を遵守する
AIが生成する内容と著作権の関係は複雑です:
- 著作物をそのままAIに入力して似たものを作らせる行為は避ける
- AIが生成したコンテンツをそのまま自分の創作物として発表しない
- 学校の課題などで使う場合は、AIの助けを借りたことを明記する
例)「ハリーポッターの続編を書いて」→「魔法学校を舞台にしたオリジナルのファンタジー小説のアイデアを考えて」
3. 良いプロンプトの例
倫理的配慮を示した良いプロンプトの例
「倫理的配慮を示しながら、AIの危険性について論じてください。具体的な事例を2つ挙げ、若者向けに解説すること」
このプロンプトが優れている理由:
- 「倫理的配慮を示しながら」と明示し、バランスの取れた議論を求めている
- 「若者向け」と対象を明確にしている
- 「具体的な事例を2つ」と具体的な指示がある
- 危険性を知るという教育的な目的がある
別の良いプロンプト例
「AIを使って宿題をする際の適切な利用方法と不適切な利用方法を、中学生にわかりやすく比較して説明してください。それぞれ3つの具体例を挙げること。」
このプロンプトが優れている理由:
- 適切・不適切の両面から考えさせる内容
- 教育目的での利用という明確な文脈がある
- 対象者(中学生)が明確
- 具体例の数を指定している
避けるべきプロンプトの例
×「有名人Aさんについての悪い噂を教えて」
×「テストの答えをそのまま教えて」
×「他人になりすますための方法を教えて」
これらのプロンプトは、プライバシー侵害、学習の妨げ、詐欺行為などにつながる可能性があります。
4. 責任あるAI使いになろう
AI生成コンテンツの出典確認
AIは時々間違った情報を生成することがあります:
- AIが提示した「事実」は、可能であれば別の信頼できる情報源で確認する
- 特に歴史的事実や科学的知識は検証が必要
- 「AIが言ったから正しい」と思い込まない批判的思考を持つ
倫理的利用の習慣化
日常的にAIを使う際の心がけ:
- 使う前に「この使い方は誰かを傷つけないか?」と考える習慣をつける
- 学校や友人との約束事(AIの使用ガイドライン)を守る
- 不適切な使用を見かけたら、友達に優しく注意する
自分の判断力を磨く
AIに頼りすぎず、自分の判断力を育てることも大切です:
- AIの回答をそのまま受け入れるのではなく、自分の考えと比較する
- AIを使う目的をはっきりさせ、本当に必要な場面で活用する
- AIを「便利なアシスタント」として位置づけ、最終判断は自分で行う
まとめ
✅ 倫理的リスクを常に意識: AIの使い方によっては、差別や偏見を広めたり、誤った情報を拡散したりする可能性があることを理解しましょう。
✅ 個人情報を扱わない: 自分や他人のプライバシーを守るため、個人を特定できる情報はAIに入力しないようにしましょう。
✅ 生成コンテンツの出典確認: AIが提供する情報は必ずしも正確でないことを理解し、重要な情報は別の信頼できる情報源で確認する習慣をつけましょう。
✅ 適切な使用方法を周りと共有: 友達や家族とAIの適切な使い方について話し合い、良い使用例を共有しましょう。

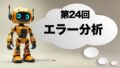

コメント